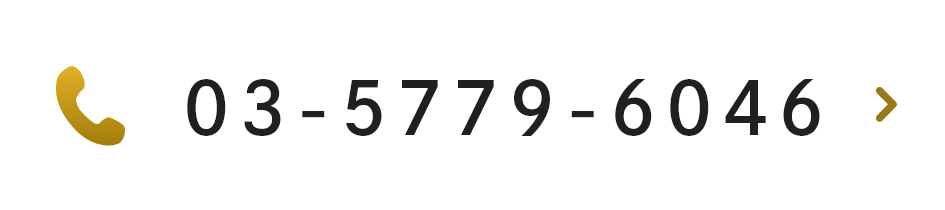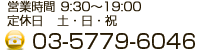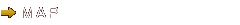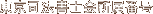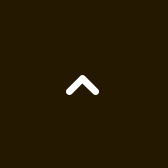相続
相続とは
相続とは、故人が生前に持っていた財産を家族や親族、場合によっては第三者が引き継ぐことです。
お亡くなりになった故人(被相続人)が、その財産(相続財産)についてなんらかの意思表示(遺言)をしていればそれに従い、
遺言をしていなければ、配偶者や子供たち、場合によっては兄弟姉妹等(法定相続人)の間で遺産分割協議をしてその財産
の配分方法を取り決めます。
もしも、相続財産に土地や建物、借地権などが含まれる場合は、相続による所有権移転登記が必要になります。
相続登記は、必ずしも相続開始後、すぐにしなければならないわけではありませんが、長期間放置しておくと、さらに相続が
発生してしまい、利害関係人が増えてしまうなど、手続きや利害調整が煩雑になってしまいます。
当事務所では、相続登記・遺言作成・遺産分割協議書作成など、相続手続きについてのお悩みを、解決に向けてのお手伝いを
いたします。
遺言書
これまであまり一般の家庭にはなじみの薄かった「遺言書」。近年ではこの遺言書の作成が増加しているようです。それは、次のような理由からではないでしょうか。
- 自分の死後、「相続」を「争続」にしたくない。
- 音信不通の家族だけでなく、お世話になった特別な人にも財産を遺贈したい。
- 人生のエンディングノートとして家族へ想いを伝えたい。
さて、その遺言書は次の2種類がよく利用されています。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
自筆証書遺言は、読んで字のごとく、本人が自ら筆をとり書面をしたためるものです。実は、法律が定める要件はとても簡単です。
- 本人が自筆する。
- 作成日付を特定する。
- 署名、押印する。
もちろん、本人の意思がしっかりしていること、誰に対して、どの財産を相続させるのか、あるいは第三者に遺贈するのか、はっきりと特定させる必要があります。また、気が変わったら後日新しい遺言でもって前回の遺言を撤回することもできます。
自筆証書遺言は、簡単で費用が比較的安く済む一方、相続開始後、遺言が見つからない場合や、家庭裁判所で※検認手続を経なければならない点、また遺言書を作成した当時の意思能力により法的に無効になるリスクがあります。
※検認とは、開封されていない遺言書や戸籍謄本を集めて、家庭裁判所において相続人立会いのもと開封、その存在を確認するための手続きです。必ずしも相続人全員が参加しなければならないわけではなく、また遺言書の有効性を裁判所が審判するものでもありません。ですから、検認を経たからといって、相続人のうち、財産を取得できない方から遺言の無効が主張されてしまうこともあり得ます。
※自筆証書遺言については、検認手続きを経ていれば、不動産の相続登記はその遺言書をもって可能です。ただし、預貯金などを相続した相続人が、その自筆証書遺言をもって単独で預貯金の引き出しが可能かどうかは各金融機関の取り扱いによりますので注意を要します。恐らく相続人全員の同意を要求してくるでしょう。
公正証書遺言は、公証役場で公証人や証人の立会のもと作成されますので、無効となるリスクは低く、(ただし、100%有効になるかといえば、そうとも言えません。当然公証人や司法書士、弁護士等の判断が後日裁判でひっくり返る事もあり得ます。)検認手続も不要のため、相続開始後すぐに名義変更手続きに移行できます。
公証役場に保管されるので、紛失のおそれもありませんが、一定の手数料がかかります。
公正証書遺言は、公証役場の公証人と事前に打合せ、内容の確認等を細かく行う必要があります。我々司法書士は、遺言者と公証役場の間に立ち、遺言書の作成から、公証人との面談まで、細かくサポートさせて頂きます。
また、公正証書遺言を作成するには、証人を2名連れて公証役場に行かなくてはなりません。(公証人出張の制度もあります)
この証人は、相続人に近い方や公証人に近い方はなることができません。司法書士が証人をお引き受けすることもありますので
併せてご相談ください。
ところで、遺言をする方は、遺言によりその財産を自由に分配することができます。ただし、民法上、相続人には遺留分という制度がありますので、留意したいものです。
また、遺言書も存在せず、相続人間で遺産分割協議もなされず(整わず)、民法に沿った法定相続分による相続がされるような場合、相続財産の分配について、特別受益や寄与分といったものを考慮することができます。
さて、遺言によって相続人ではない方に財産を与える事も可能です。遺贈といわれるもので、特別な方に特定の財産(不動産)を与えることが多いでしょうか。
ここで注意を要することとしては、遺言執行者として遺贈を受ける方を書いておかないと不動産の名義変更の手続きが難しくなること、遺贈により、加算された相続税がかかり、不動産登記を受ける際の登録免許税が相続人への移転に比べて多額になること、借地上の建物の場合は、地主へ譲渡承諾料の支払いが必要になってくることです。思わぬ現金を用意しなければならない事態も考慮して遺言をすることも必要になります。
遺産分割

相続開始後は、遺言書が存在すればそれを尊重して財産を分けることになりますが、遺言書が存在しない場合や、法定相続として、全財産を相続人で共有とするには、様々な不都合が生じることから、相続財産の現物をそれぞれの相続人へ振り分け、分割することになります。
財産の種類や数から現物の分割ができない場合には、一定の相続人へ相続財産を集中させ、代わりに金銭等を残りの相続人に代償する方法や、相続財産を換価して分割する方法もあります。
この遺産分割は、相続人の全員による合意が必要です。まずは、亡くなった方の出生までの戸籍を全て収集して、隠れた相続人がいないかどうかを確認する必要があります。養子縁組や認知された非嫡出子、被相続人よりも先にお亡くなりになった子供の子供(代襲相続人)などの存在を戸籍を全て解読して洗い出す必要があります。
そのうえで、全員の合意により、具体的な分配をしてそれぞれ実印で協議書へ押印をし、印鑑証明書を提出してもらいます。
財産の特定方法についても、例えば不動産ならば住所ではなく、地番や家屋番号をもって特定するなど、後日にあいまいな表示によって争いが起きないように配慮します。
当事務所では、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成から、土地や建物など不動産の名義変更(相続登記)をお手伝いさせて頂きます。
相続人の協議が整わない場合には、家庭裁判所へ遺産分割の調停を申し立てることになりますが、それでも調停が整わない場合には審判にゆだねることになります。司法書士には家庭裁判所での代理権がございませんので、事案によっては、提携した法律事務所をご案内いたします。
遺留分
遺言をする方は、相続分の割合を決めたり、その財産を自由に分配(遺産分割方法の指定)することができますが、公平の観点から、民法では各相続人に対して一定の割合の財産取得を保障する制度を用意しています。
これが遺留分という権利です。
もちろん、遺留分は、あくまで相続人が主張できる権利であって、これに反する遺言も可能です。ただ単に、相続人から後日(相続開始及び減殺できる贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内、または相続開始から10年以内)主張された場合にはその部分に限って財産の一部を返還しなければならないという趣旨です。
遺留分を算定する際の相続財産については、過去に相続人に対してした特別受益にあたる贈与、相続開始前1年間にした第三者に対する贈与(1年以上前でも、遺留分を害することを知ってした贈与)、遺贈の額を算入して債務の合計額を控除します。そのうえで、下に記載している遺留分の割合をかけたものが具体的な遺留分となります。
このように、遺留分は血縁に対して法律が保障する最低限の権利であり、遺言その他の方法で排斥することはできません。
遺留分を排斥する結果となるものとして、遺留分の放棄(相続人自らの申し出と家庭裁判所の許可が必要)、※相続人の廃除、※相続欠格がありますが、その要件はとても厳しいものです。
相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てることで相続放棄をすることも考えられますが、この場合は代襲相続は発生しません。
※生前や遺言(遺言執行者の選任も要します)により相続人を廃除する制度がありますが、被相続人に対して虐待や重大な侮辱、著しい非行のあった相続人を相続から廃除するものですが、その程度や証明が難しく、戸籍に記録され、また代襲相続されてしまうなど、現実的にはあまり実益がない場合も多いのではないでしょうか。
※相続欠格とは、被相続人、他の相続人に対する殺人や殺人未遂、詐欺や強迫などにより遺言書に手を加えさせたり、遺言書を隠匿した場合など、相続人としての地位を否定するものです。これも代襲相続の対象となります。
さて、具体的に各相続人に保障された遺留分の割合は次のとおりです。
- 父母のみが法定相続人になる場合、その法定相続分の3分の1
- それ以外の場合は全て、法定相続分の2分の1
- 兄弟姉妹には遺留分がありません
法定相続による相続分
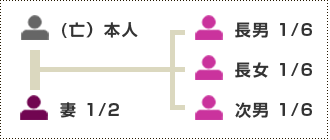
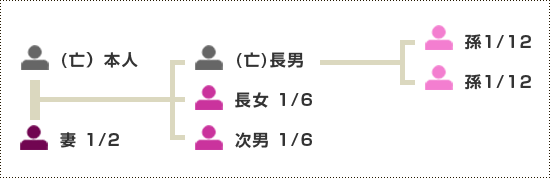
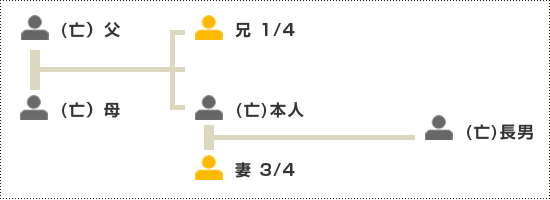
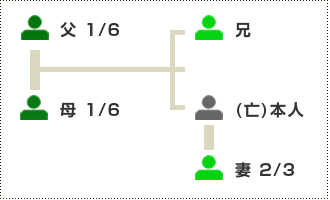

寄与分
亡くなった方に生前、特別の寄与をして、その財産形成に特別の影響を与えた相続人に対して、民法ではその法定相続分等に寄与分を加えることを認めています。
ただし、次のような点を注意しなければなりません。
- 相続人による通常の家事は含まない
- 相続人による通常義務としての扶養、看護は含まない
- 相続人による労務提供が相当対価でされた場合は含まない
相続人の協議でまとまらなければ家庭裁判所へ調停の申し立てを行います。
特別受益

相続人が、亡くなった方から生前贈与を受けていた場合、それを相続財産の前渡しとしてとらえ、その贈与された価額をいったん相続財産に加えて、各相続人の法定相続分を計算します。そして、贈与を受けていた相続人は、そこから贈与されていた額を引いて具体的相続分として相続することになります。
この特別受益による計算は、遺言により、考慮させないこともできます。(持ち戻し免除)
遺言により持ち戻し免除の意思表示がされていても、遺留分を算定するための基礎財産としてはその特別受益を算入します。
それでは、持ち戻しがされる生前贈与はどのようなものを含むのでしょうか。
嫁入り道具や支度金、持参金、商売資金、不動産や住宅取得資金などが考えられます。通常の学資や小遣い銭などは含まないとされます。死亡保険金については争いがあります。
相続とは
相続とは、故人が生前に持っていた財産を家族や親族、場合によっては第三者が引き継ぐことです。
お亡くなりになった故人(被相続人)が、その財産(相続財産)についてなんらかの意思表示(遺言)をしていればそれに従い、
遺言をしていなければ、配偶者や子供たち、場合によっては兄弟姉妹等(法定相続人)の間で遺産分割協議をしてその財産
の配分方法を取り決めます。
もしも、相続財産に土地や建物、借地権などが含まれる場合は、相続による所有権移転登記が必要になります。
相続登記は、必ずしも相続開始後、すぐにしなければならないわけではありませんが、長期間放置しておくと、さらに相続が
発生してしまい、利害関係人が増えてしまうなど、手続きや利害調整が煩雑になってしまいます。
当事務所では、相続登記・遺言作成・遺産分割協議書作成など、相続手続きについてのお悩みを、解決に向けてのお手伝いを
いたします。
遺言書
これまであまり一般の家庭にはなじみの薄かった「遺言書」。近年ではこの遺言書の作成が増加しているようです。それは、次のような理由からではないでしょうか。
- 自分の死後、「相続」を「争続」にしたくない。
- 音信不通の家族だけでなく、お世話になった特別な人にも財産を遺贈したい。
- 人生のエンディングノートとして家族へ想いを伝えたい。
さて、その遺言書は次の2種類がよく利用されています。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
自筆証書遺言は、読んで字のごとく、本人が自ら筆をとり書面をしたためるものです。実は、法律が定める要件はとても簡単です。
- 本人が自筆する。
- 作成日付を特定する。
- 署名、押印する。
もちろん、本人の意思がしっかりしていること、誰に対して、どの財産を相続させるのか、あるいは第三者に遺贈するのか、はっきりと特定させる必要があります。また、気が変わったら後日新しい遺言でもって前回の遺言を撤回することもできます。
自筆証書遺言は、簡単で費用が比較的安く済む一方、相続開始後、遺言が見つからない場合や、家庭裁判所で※検認手続を経なければならない点、また遺言書を作成した当時の意思能力により法的に無効になるリスクがあります。
※検認とは、開封されていない遺言書や戸籍謄本を集めて、家庭裁判所において相続人立会いのもと開封、その存在を確認するための手続きです。必ずしも相続人全員が参加しなければならないわけではなく、また遺言書の有効性を裁判所が審判するものでもありません。ですから、検認を経たからといって、相続人のうち、財産を取得できない方から遺言の無効が主張されてしまうこともあり得ます。
※自筆証書遺言については、検認手続きを経ていれば、不動産の相続登記はその遺言書をもって可能です。ただし、預貯金などを相続した相続人が、その自筆証書遺言をもって単独で預貯金の引き出しが可能かどうかは各金融機関の取り扱いによりますので注意を要します。恐らく相続人全員の同意を要求してくるでしょう。
公正証書遺言は、公証役場で公証人や証人の立会のもと作成されますので、無効となるリスクは低く、(ただし、100%有効になるかといえば、そうとも言えません。当然公証人や司法書士、弁護士等の判断が後日裁判でひっくり返る事もあり得ます。)検認手続も不要のため、相続開始後すぐに名義変更手続きに移行できます。
公証役場に保管されるので、紛失のおそれもありませんが、一定の手数料がかかります。
公正証書遺言は、公証役場の公証人と事前に打合せ、内容の確認等を細かく行う必要があります。我々司法書士は、遺言者と公証役場の間に立ち、遺言書の作成から、公証人との面談まで、細かくサポートさせて頂きます。
また、公正証書遺言を作成するには、証人を2名連れて公証役場に行かなくてはなりません。(公証人出張の制度もあります)
この証人は、相続人に近い方や公証人に近い方はなることができません。司法書士が証人をお引き受けすることもありますので
併せてご相談ください。
ところで、遺言をする方は、遺言によりその財産を自由に分配することができます。ただし、民法上、相続人には遺留分という制度がありますので、留意したいものです。
また、遺言書も存在せず、相続人間で遺産分割協議もなされず(整わず)、民法に沿った法定相続分による相続がされるような場合、相続財産の分配について、特別受益や寄与分といったものを考慮することができます。
さて、遺言によって相続人ではない方に財産を与える事も可能です。遺贈といわれるもので、特別な方に特定の財産(不動産)を与えることが多いでしょうか。
ここで注意を要することとしては、遺言執行者として遺贈を受ける方を書いておかないと不動産の名義変更の手続きが難しくなること、遺贈により、加算された相続税がかかり、不動産登記を受ける際の登録免許税が相続人への移転に比べて多額になること、借地上の建物の場合は、地主へ譲渡承諾料の支払いが必要になってくることです。思わぬ現金を用意しなければならない事態も考慮して遺言をすることも必要になります。
遺産分割
 相続開始後は、遺言書が存在すればそれを尊重して財産を分けることになりますが、遺言書が存在しない場合や、法定相続として、全財産を相続人で共有とするには、様々な不都合が生じることから、相続財産の現物をそれぞれの相続人へ振り分け、分割することになります。
相続開始後は、遺言書が存在すればそれを尊重して財産を分けることになりますが、遺言書が存在しない場合や、法定相続として、全財産を相続人で共有とするには、様々な不都合が生じることから、相続財産の現物をそれぞれの相続人へ振り分け、分割することになります。財産の種類や数から現物の分割ができない場合には、一定の相続人へ相続財産を集中させ、代わりに金銭等を残りの相続人に代償する方法や、相続財産を換価して分割する方法もあります。
この遺産分割は、相続人の全員による合意が必要です。まずは、亡くなった方の出生までの戸籍を全て収集して、隠れた相続人がいないかどうかを確認する必要があります。養子縁組や認知された非嫡出子、被相続人よりも先にお亡くなりになった子供の子供(代襲相続人)などの存在を戸籍を全て解読して洗い出す必要があります。
そのうえで、全員の合意により、具体的な分配をしてそれぞれ実印で協議書へ押印をし、印鑑証明書を提出してもらいます。
財産の特定方法についても、例えば不動産ならば住所ではなく、地番や家屋番号をもって特定するなど、後日にあいまいな表示によって争いが起きないように配慮します。
当事務所では、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成から、土地や建物など不動産の名義変更(相続登記)をお手伝いさせて頂きます。
相続人の協議が整わない場合には、家庭裁判所へ遺産分割の調停を申し立てることになりますが、それでも調停が整わない場合には審判にゆだねることになります。司法書士には家庭裁判所での代理権がございませんので、事案によっては、提携した法律事務所をご案内いたします。
遺留分
遺言をする方は、相続分の割合を決めたり、その財産を自由に分配(遺産分割方法の指定)することができますが、公平の観点から、民法では各相続人に対して一定の割合の財産取得を保障する制度を用意しています。
これが遺留分という権利です。
もちろん、遺留分は、あくまで相続人が主張できる権利であって、これに反する遺言も可能です。ただ単に、相続人から後日(相続開始及び減殺できる贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内、または相続開始から10年以内)主張された場合にはその部分に限って財産の一部を返還しなければならないという趣旨です。
遺留分を算定する際の相続財産については、過去に相続人に対してした特別受益にあたる贈与、相続開始前1年間にした第三者に対する贈与(1年以上前でも、遺留分を害することを知ってした贈与)、遺贈の額を算入して債務の合計額を控除します。そのうえで、下に記載している遺留分の割合をかけたものが具体的な遺留分となります。
このように、遺留分は血縁に対して法律が保障する最低限の権利であり、遺言その他の方法で排斥することはできません。
遺留分を排斥する結果となるものとして、遺留分の放棄(相続人自らの申し出と家庭裁判所の許可が必要)、※相続人の廃除、※相続欠格がありますが、その要件はとても厳しいものです。
相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てることで相続放棄をすることも考えられますが、この場合は代襲相続は発生しません。
※生前や遺言(遺言執行者の選任も要します)により相続人を廃除する制度がありますが、被相続人に対して虐待や重大な侮辱、著しい非行のあった相続人を相続から廃除するものですが、その程度や証明が難しく、戸籍に記録され、また代襲相続されてしまうなど、現実的にはあまり実益がない場合も多いのではないでしょうか。
※相続欠格とは、被相続人、他の相続人に対する殺人や殺人未遂、詐欺や強迫などにより遺言書に手を加えさせたり、遺言書を隠匿した場合など、相続人としての地位を否定するものです。これも代襲相続の対象となります。
さて、具体的に各相続人に保障された遺留分の割合は次のとおりです。
- 父母のみが法定相続人になる場合、その法定相続分の3分の1
- それ以外の場合は全て、法定相続分の2分の1
- 兄弟姉妹には遺留分がありません
法定相続による相続分
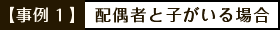
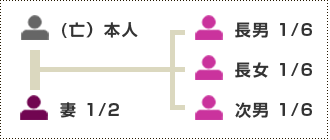
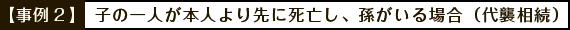
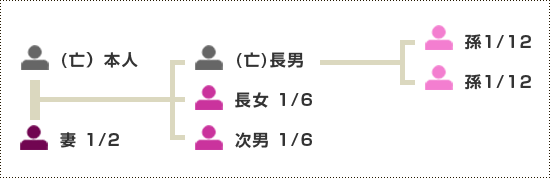

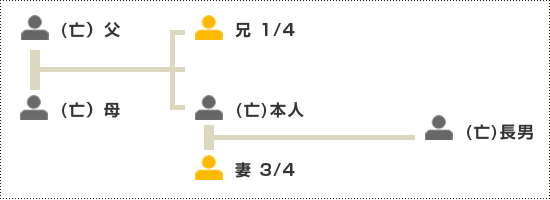
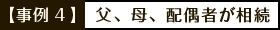
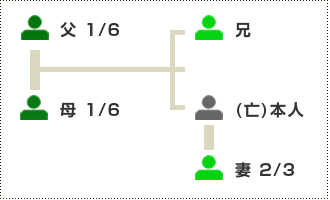
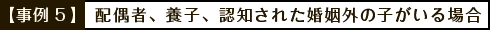

寄与分
亡くなった方に生前、特別の寄与をして、その財産形成に特別の影響を与えた相続人に対して、民法ではその法定相続分等に寄与分を加えることを認めています。
ただし、次のような点を注意しなければなりません。
- 相続人による通常の家事は含まない
- 相続人による通常義務としての扶養、看護は含まない
- 相続人による労務提供が相当対価でされた場合は含まない
相続人の協議でまとまらなければ家庭裁判所へ調停の申し立てを行います。
特別受益

相続人が、亡くなった方から生前贈与を受けていた場合、それを相続財産の前渡しとしてとらえ、その贈与された価額をいったん相続財産に加えて、各相続人の法定相続分を計算します。そして、贈与を受けていた相続人は、そこから贈与されていた額を引いて具体的相続分として相続することになります。
この特別受益による計算は、遺言により、考慮させないこともできます。(持ち戻し免除)
遺言により持ち戻し免除の意思表示がされていても、遺留分を算定するための基礎財産としてはその特別受益を算入します。
それでは、持ち戻しがされる生前贈与はどのようなものを含むのでしょうか。
嫁入り道具や支度金、持参金、商売資金、不動産や住宅取得資金などが考えられます。通常の学資や小遣い銭などは含まないとされます。死亡保険金については争いがあります。